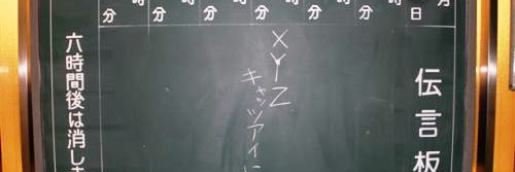
もむ
@momentumyy
山田祐樹 (Yuki Yamada) 九州大学基幹教育院 准教授。深い山中で認知系の心理してます。好きなことは犬触りです。だからアイコンは完全にスヌーピーです。 心理学を遊撃する本: https://amzn.asia/d/ek38NHQ Google Scholar: http://bit.ly/3EhtLFY
そういえば遊撃本が出ました。別に壮大なスペクタクルでもなく雑談も多めですが、一般的な心理学の本ではなかなか見かけないような話で埋め尽くされていると思います。そんなとこまで含めて心理学が好きなので、似たような物好きな方が増えたらいいなと思います。 amzn.asia/d/enECX7Q

「博士課程に給料を出す世界」というのは「学振に通った人のみ進学可」で達成できるし,海外のメジャーどころの大学の倍率は学振より高い分上記をより厳しい水準で実現している.ただ,それが望ましい世界かと言われたらそうは思わないんだよね.
若手研究者の会とか、学会シンポジウムの演者の所属を調べると、多様性の低下が著しいです。それだけ研究ができる場が減っているわけです。一つひとつの拠点はもしかしたら予算が増えているのかもしれませんが、同じテーマの研究者数が増えても全体にとってはプラスとは言えないでしょう。
チームみらい、 長野で得票率が最も高い自治体:軽井沢 千葉で得票率が最も高い自治体:流山 埼玉で得票率が最も高い自治体:和光 茨城で得票率が最も高い自治体:つくば 兵庫で得票率が最も高い自治体:芦屋 誤差レベルとは言え、これは面白い結果
この記事の書き方は、問題ありと思う。そもそも横断研究で、因果関係を決定するものではない。調査は自己申告で思い出しバイアスあり。参加者は地方の大企業の社員。論文にはlimitationがきちんと書いてあるのに、新聞が取り上げると「日本食はすばらしい」になってしまう。 asahi.com/articles/AST7L…
当時非常に衝撃だったのを覚えてます。15年かかったのか…本件はオープンサイエンスや出版後査読についていろいろと考えさせられます。結局FelisaのJobはかなり転々としたようですが、ちょうど研究に復帰したばかりだったんですね。
NASAの研究者による2010年のヒ素細菌論文のScience誌からの撤回。分子生物学の蓄積を否定する内容でありながら、不十分な証明しかできておらず、査読が機能していない例です。発見された細菌名の由来からもうかがえますが、承認欲求が強すぎる研究者といえるでしょう。 science.org/content/articl…
授業アンケートで人権を傷つけられるレベルのことをいくつか書かれてかなり深く落ち込んでいますが、最寄り駅の自転車置き場のスタッフさんの優しさが身にしみました。次のアンケートでは死ぬ気で挽回します。しかし……思うことはわかりますが、言葉遣いだけはやはり気をつけてほしいです、、、
これまじみんな使ってね
Interested in love and mate preferences? Our dataset includes responses from 117,293 participants across 175 countries. You're welcome to use it for your own research! Paper and dataset linked below. @ with amazing collaborators from the large-scale cross-cultural consortium <3
ゲーム開発に「心理学」を用いるならば「◯◯バイアス」みたいな分かりやすい概念を鵜呑みにすべきではない?“新たな一歩”を加えるための考え方【CEDEC2025】 gamer.ne.jp/news/202507230… #CEDEC2025
心理学者の専門別の特性を調べてる論文(Sulik et al., 2025)、ローデータが公開されているので見てみたら、認知心理学者はもはやコンピューターアナロジーを大して有用だと思っていないことがわかった(まあ、 今と1960 ~ 80年で感覚同じなわけないし、さもありなん) nature.com/articles/s4156…
Scientists overwhelmingly recognize the value of sharing null results, but rarely publish them in the research literature go.nature.com/472poOC
来た来た来た!ピボットテーブル自動更新!(元のデータに変更があれば、その瞬間ピボットテーブルも更新される) これはめちゃくちゃ良いアプデ
PNASに出た論文解説。 "テニュアを付与された後の論文発表数は分野によって異なり、生物学者など実験室で研究を行う傾向のある研究者は横ばいとなる一方、数学など実験室での研究をあまり必要としない分野の研究者は減少する。" nature.com/articles/d4158…