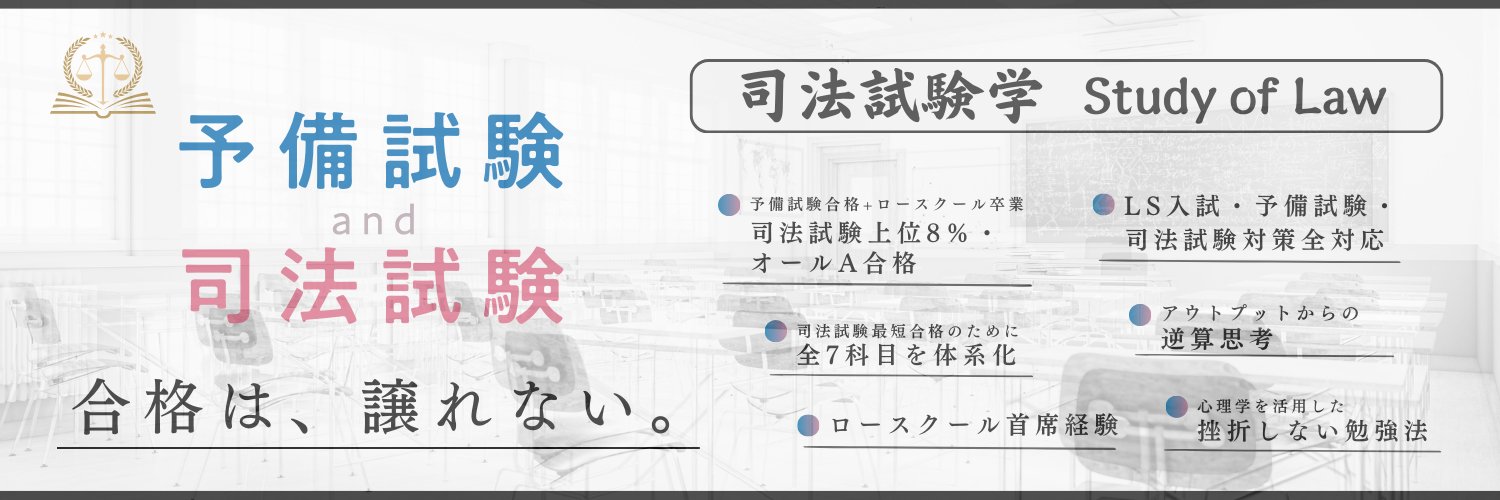
ホウノリ@『司法試験学』考案者
@nt_hn7
司法試験・予備試験の勉強法を最適化⇨最短合格へ|クラオリファイ代表(公開準備中)|弁護士|結果無価値論者|予備試験合格|司法試験オールA合格|早慶(学部)卒|オールA合格|上位LS首席経験(全額免除)|心理学|脳科学|挫折しない勉強法|
【ホウノリ初の無料企画】 *オールE・2000番台以下でも1年で司法試験オールA合格を掴み取る* 【司法試験学】令和7年合格『スタートダッシュ』セット ついに開始しました! <参加条件> ・このポストに「いいね」 ・ホウノリ(@nt_hn7)をフォロー ・「スタート」とリプライ…

次の①②について、bはaの批判になっているか。 ① a:自然数1は自然数2である。 b:自然数1は自然数1である。 ② a:おたまじゃくしであるXは人間に変態する。 b:Xはおたまじゃくしである。
bの見解はaの見解に対する批判になっているか。 a:資本主義憲法からの共産主義への移行は可能である。 b:資本主義とは私有財産制を可能とする原理である。
Xの自殺の自由(a)に対して、Xの自己決定権(b)は否定原理でもあり肯定原理でもあるので、批判になるか?と聞かれればYesと答えざるを得ない(根拠になるかと問われてもYes)。あの問題はそれとほぼ同じ構造なのではないかと。…
単なる日本語の問題として捉えるとそうなりますよね。 ただ法学の問題としてみると、宮沢と芦部で正当性の契機と権力性の契機の内容が逆なので、この問題で理解が問われている正当性の契機とは何なのかは不明です。やはり単なる日本語の問題なんでしょうかね。
国民主権原理を権力性の契機で理解すると国民自身が権力コントロールをする必要があるから独裁制が採用できないが、国民主権原理を正当性の契機で理解すると国民自身による権力コントロールは不要で独裁制を採用し得る。そうするとbはaの根拠であって批判ではない、と解くのかなぁと。
刑法各論のわかりやすい答案の書き方【法律ステップアップ講座】|ホウノリ@"司法試験学" note.com/santiago_old/n… 80,000view突破しました。 期末試験シーズンに毎回5000~6000ぐらい見られています。

設問の「根拠となる」というのは、一部でも根拠となればいいのか、すべての記述の根拠とならねばならぬのか、全くもってわかりにくいですよね笑。
国会主権原理は国会の制定した制定法の徹底すなわち裁判所による法適用保障を含んでも、制定法ではないコモンローの法適用保障までは必ずしも含まないのでアは2。国民主権原理を採用しても形式的法治主義は採用しうるのでウは2。と考えました。
短答で予備校の答案が割れてると学生から聞いた。問題は、国会主権が法の支配の論拠となるかというもの。ダイシーは国会主権が法の支配を支えると明確に論じている。しかし、愛敬先生がリンク先の論文50頁脚注10で指摘するようにダイシーのこの部分は説得力は現代ではほぼないwaseda.jp/folaw/icl/asse…
全くの推察なのですが、この短答の原案作成者はむしろ法の支配やイギリス憲法の専門外の人で、ダイシーがいっているからと作問し、1を正解として用意した。他の研究者委員も、「ダイシーが言っているので根拠になり得ること自体は否定できないなあ、よしっ」となって出てきたのではないかと思います
kotobank.jp/word/%E6%86%B2… 樋口陽一が執筆してるこの記事を見れば、本問がシュミットを元にしていることは明らか。 であるならば、正当性の契機はむしろシュミットが論拠にしているので、 bは批判にならないから2となる。 (そんな問題を出して良いのかという疑問があるので1説は捨てがたい)
民主主義と独裁が両立すると言っているのはシュミットのようです。 そうすると、a.はシュミットから引っ張ってきていることが濃厚。(少なくとも意識はしている。) シュミットは始源的で無制約な憲法制定権力を説くので、bが憲法制定権力や憲法改正権力を持ち出したところで、批判にならない。…
note.com/santiago_old/n… Xに出すか迷いましたが、ナチスの全権委任法が司法-憲法短答[第11問]の反例たり得ない理由を昨日、noteに詳しめに書いておきました。 一言でいうと、ナチスの全権委任法は法学的には「革命」「クーデター」であり、法学的に正当化されていないからです。…

司法憲法〔第17問〕 これは211でしょう。 アは判例のレイシオと付随的違憲審査制が関係ないから2。 イはなるべく憲法判断回避の準則の根拠になり得るから1。…