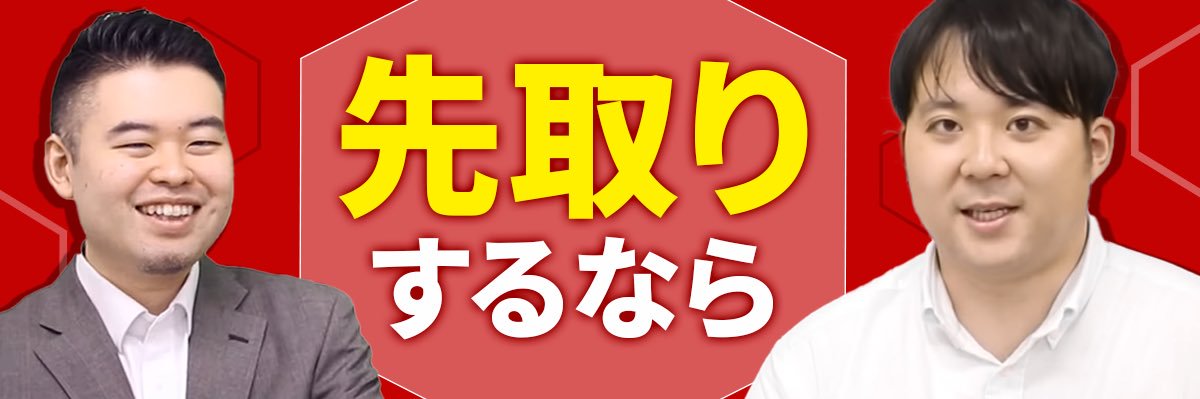
コバショー【CASTDICE TV】
@kobasho_cd
個別指導塾CASTDICE塾長→http://castdice.jp 講師・スタッフ募集中!◆『最高の職業と進路が見つかるガイドブック』『ゼロから知りたい総合型選抜・学校推薦型選抜』など執筆◆講演承ります◆YouTube:CASTDICE TV◆質問DM不可◆小林尚
夏期講習での塾選び、料金や合格実績の数字だけで決めるのは本当に危険。 最も重要なのはあなたの学習を最適化し、時間を無駄にさせない環境か否か。 また、親御さんの過干渉で本人の当事者意識が削がれるケースも散見される。 家庭も含めた総合的な戦略が、大学受験では強く求められています。
GMARCHに落ちる受験生には共通点があります。 英単語が終わらない 言い訳がうまい 計画が甘い 耳が痛くても、これが現実です。 動画でも話しましたが、特別な才能は不要。 当たり前のことを当たり前にやる、その愚直さが合格への最短距離です。 自分に甘えているなら、今決意しよう!
大学受験における学力と遺伝の関係はよく話題になるが、才能だけで合格できるほど甘くはない。 むしろ大学側は、膨大な試験範囲をやり切る「努力を継続できる才能」を求めている。遺伝的素養は初期値に過ぎない。本番で問われるのは、正しい戦略に基づき、いかに努力を積み重ねてきたかである。
夏の勉強で焦って全科目に手を出すのは悪手です。 特に難関大学を目指すなら、英語と数学の基礎固めが最優先事項。 高3になるまでに範囲学習を完璧にするのが理想だったが、遅れているなら夏で取り返すしかない。 周りに流されず、自分の課題から目を背けない勇気が合格を引き寄せます。
これだけ共通テストが難しいと、もはや国立難関大は「逆転」という発想がそもそも困難。 先取り&勉強量でぶっちぎるしかない。 「早く始めて、莫大な量をやってぶっちぎる」
私の年齢になると、親が病気、入院、はたまた…という話も珍しくありません。 受験生にはまだ分かりにくい感覚かもしれませんが、親孝行…はまだ早くても、親御さんへの感謝の気持ちを持って勉強してください。 できれば、たまにで良いので感謝の言葉を伝えてください。きっと喜んでくれますよ。
誰でも人を批判をするのは簡単です。なぜなら「他人のこと」だからです。一番難しいのは、自分自身の行動を変えることです。 後者ができるかできないかで人生が変わります。
これまで勉強してこなかった人が明日からいきなり1日5時間とか6時間勉強するのは困難なことです。 つまり合格に必要な勉強時間を、受験当日までの残り日数で割っても、それは机上の空論でしかなく実行性はありません。 だからこそ、早くから始めて習慣化を図るべきなのです。
「学校の宿題は無視して良いですか?」 →最終的には自分の自由と責任。 その宿題は本当に全て無駄ですか? 未習得単語や教科書レベルの数学の問題とか、今のあなたに必要なことも含まれているかも。 その取捨選択ができない人は、受験勉強でも最適なスケジュールを組むことはできません。
受験勉強の本質は 「昨日できなかったことを、今日できるようにする」 ことの繰り返しです。 もちろんやり方次第でどれだけ達成できるかは異なりますが、とにかく昨日の自分よりもレベルアップできたと毎日感じられれば、結果は自然と出てくるものです。
お子さんのやる気がないと嘆く前に、保護者様ご自身の情報リテラシーは十分ですか? 学校や塾からの客観的な分析を素直に受け入れ、共に戦略を考えられるかが重要です。 現代の複雑な受験では、親御さんのマネジメント(≠単なる強制)スキルがお子さんの学力以上に合否を左右するかもしれません。
大学受験のゴールは合格ではない。特に文系はその傾向が強い。 入学後に得られる時間を活用し、いかに社会で通用するスキルを身につけるかが重要。 理系が研究に時間を費やす中、文系は実践的な経験を積める。 時間的アドバンテージを活かせば、就活でも成功できる。文系よ、立ち上がれ!
受験生も大人も、みんな「時間をかけて成果を出す」ことを嫌います。 成績をすぐ上げたい。 浪人はしたくない。 今すぐ昇進したい。 早くお金持ちになりたい。 気持ちはわかりますが、私は「ゆっくり」成果を出しても良いと思います。最終的に「そこに立ち続けている人」が勝者です。
現代の大学受験において先取り学習はもはや選択肢ではない。 探求学習や課外活動で多忙な高校生活、多様化する入試形式を考えれば、高3から始めるのでは間に合わないのが現実だ。 難関大を目指すなら、高1から計画的に主要科目を固めていくことが、現役合格への唯一の道である。
note記事、「私の教育答え合わせ」さんにて、私の小学生〜高校生までの勉強、塾の活用、習いごとについて一気にまとめていただきました! 普段YouTubeでもなかなかここまでまとめてお話しすることはないので、是非読んでみてください! もちろん無料です! note.com/karashikashi/n…

親御さんの「うちの子は本当はもっとできるはず」という気持ちは痛いほど分かります。しかし、その主観が受験戦略の最大の足枷になることも。 まずは塾や学校が示す客観的なデータ、いわゆる「設定」を真摯に受け止めることが、本当のスタートであり、合格への最短距離を歩むための第一歩なのです。
大学入試多様化は、受験生に戦略の複雑化と学習負担増大を招きます。 早期準備や学習環境の重要性が増し、情報・経済格差も影響。 大学側は定員確保で推薦枠を拡大し、学力低下や「中学校化」も。 難関大の価値が高まる中、入試制度が学生と大学双方に課題を突きつけています。
お子さんの受験への干渉、それは「マネジメント」ですか、それとも単なる「管理」ですか? 子の主体性を尊重し共に戦略を練るのが前者。 親の主観で一方的に支配するのが後者。 この本質的な違いを理解できなければ、お子さんの努力は水の泡になります。
受験勉強、やる気が出ない? 甘い。 今は「大学には入りやすい」ものの、実態はBF大学の台頭で教育は二極化している。 安易な進学は、結局のところ学力不足と就職難に直結します。 就活の筆記試験の算数すら解けない大学生になるのか? 戦略的に進路を選び、目標に向けて徹底的に学んでほしい。