
かねたく
@hirakuk
本好きの日本史研究者。つぶやくのはもっぱら本と古い映画と絵のことばかり。
毎度思うが、ラピュタ阿佐ヶ谷は久しぶり。23年9月以来のようで約2年ぶりではないか。去年全く来ることができていないのか。ひどすぎる。この水の江滝子特集も気づいた時には折り返し点を過ぎていた。家とは逆方向なのでつい億劫になるが、こうして映画を観ると愉しい気分になるのだから。
「街から街へつむじ風」の舞台になった病院のある坂道の街はどこか?赤坂あたりかと思ったら、道玄坂(正確には246沿い)らしく驚いた。道路の中央に首都高の高架がこれから建つ工事中の段階。坂の上から見晴らしよく山手線の線路が見える。今の246(と首都高)の姿からは想像できない。
2冊目・3冊目。柳原良平『アンクルトリス交遊録』。これも前の版の旺文社文庫版は持っているはず。芥川也寸志『私の音楽談義』。「音楽」は毎日触れているが基本的なことには無知な者にとって、目次を見ただけでワクワクするような内容。芥川比呂志・也寸志兄弟は本業以外もすごい。
書籍部の文庫新書3冊15%引フェア。中公文庫の新刊で欲しいものがちょうど3冊あった。久生十蘭(日下三蔵編)『平賀源内捕物帳』。安田顕さんが演じて話題になった大河ドラマ絡みで源内が浮上してきたのだろうと思うが、どういうきっかけであれ再刊は嬉しい。朝日文芸文庫版は持っているはず。
帰宅後せっかく鷗外全集があるので、積まれた中から第一巻を探し出す。鷗外全集を読む閑雅な休日、いつもこんな休みを過ごせたら。授業で読んだ時どういう感想を持ったのかは忘れた。主人公はひどいやつだと思うが、親身になって心配する親友相澤(モデルは賀古鶴所)への感謝の思いが強く印象に残る。
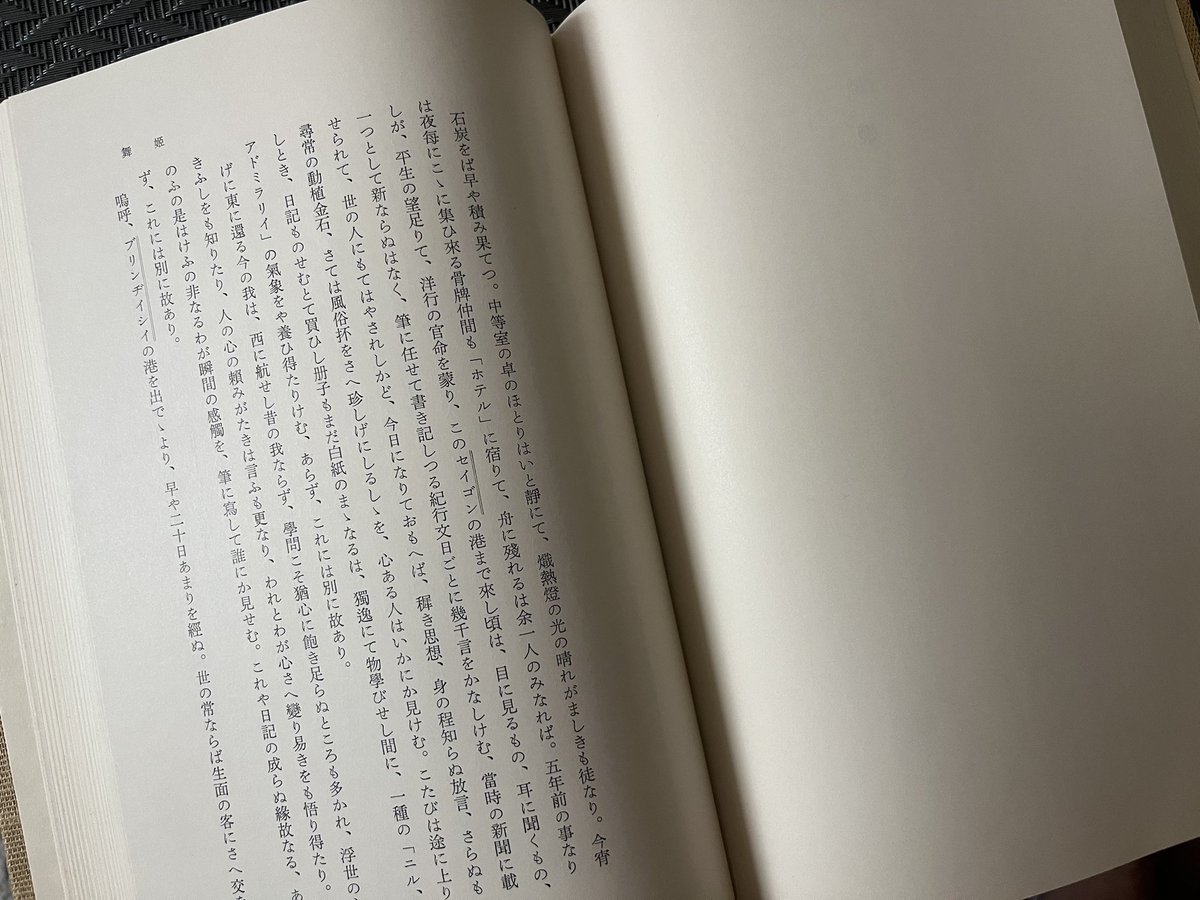
朝イチ展覧会。文京区立森鷗外記念館のコレクション展「小説『舞姫』をよんでみよう!」を観る。この展示でもあったが、国語の授業で『舞姫』を読んだ。それ以来だろう。高校生の時だとしても40年ぶりか。展示は、舞姫の自筆原稿復刻版を中心に、加筆修正の跡をたどり、作品評を示す。
髙島野十郎展は巡回して一年後に渋谷区立松濤美術館で開催される。彼は渋谷や青山に居を構えていたことがあり、とくに渋谷には縁が深いようだ。神宮前(いまの原宿)あたりに住んでいたという。一年後、そのときも元気に髙島野十郎展を観ることができていますように。
髙島野十郎は晦渋な表情の自画像も特徴的で、よく知られる自画像のほか数点の自画像が展示されており、それらすべてが異様な緊張感を湛えていて印象深い。東京帝国大学農学部水産学科を首席で卒業しながら、卒業後絵の道を選んだ。しかし大学時代の恩師の肖像画も描き、反目したわけではない。
個人的に髙島野十郎作品で好きなのは風景画だ。とくに田園風景。雑草の一本一本、葉の一枚一枚もおろそかにしないと思われるほど細かく丁寧に書き込む。有明海を描いた「春の海」の前でしばし佇んだ。緑の中流れる小川を描く「草間の小川」、野中の一本道「夏雲」、深々と降る雪の風景「積る」など。
髙島の絵は、この蠟燭の炎や、太陽、月など光の描き方が印象的だ。太陽はゴッホ的であり、萬鐵五郎の太陽にも通じる。月は夜空に満月だけ描かれるという特異なものから、月明かりに浮かぶ雲や草木の影が描かれるものまで多彩。月明かりによって微妙に異なる夜空の階調がすばらしい。
静物画はリアルで、たしかに劉生作品を思い起こさせる。髙島野十郎と言えばチラシにもなっている蠟燭の絵だが、同じ主題(しかし微妙に異なり、支持体も板やキャンバスなど異なる)の絵が10点以上展示されていて驚いた。大切な主題で、親しい人に贈るために多く描いたという。たしかに個人蔵が多い。
この「征戦愛馬譜 暁に祈る」では、徳大寺伸の父で、嫁に来た田中絹代を慈しみ、彼女の勘当をどうにか解こうと苦労する義父の河村黎吉がいいんだよなあ。徳大寺の親友で、かつて田中を好きだった騎馬兵の夏川大二郎も存在感がある。
購入本その6。渡辺一夫(串田孫一・二宮敬編)『敗戦日記』(ちくま学芸文庫)。元版(1995年刊)は持っていないはず。川崎長太郎『女のいる暦』(講談社文芸文庫)。生涯で関わった女性たちを描く「著者唯一の書き下ろし長篇小説」とのこと。講談社文芸文庫はこういう本をもっと出してほしい。