
KJ_OKMR
@OKMRKJ
Professor of Law (Intellectual Property Law & In-House Legal Practice), Keio Univ. Law School, Japan:アイコンはHMDを装着しているところの第3バージョン。パススルー機能のおかげで自撮りも楽々。
最近やっと、レジで、スムーズにoliveのタッチ決済ができるようになった。 でも、セブンアプリで会員番号スキャンしてもらってからのoliveタッチ決済はまだ苦手。
なるほど。このレポート見ると、米国にとっても、この段階で車の関税を15%にしたのは合理的な行動なんだなと。輸出企業が関税分を負担できなくなって米国消費者に転嫁されると個人消費が冷え込み支持率も下がる・・・ 15%なら負担し続けてくれるだろうということかな mizuho-rt.co.jp/publication/20…
田中辰雄先生の分析。なるほど、勉強になるなあと思いながら読んだ。一点だけ、この記事でも使われている「岩盤保守層」という言葉がいつも気になってる。「○○の岩盤支持層」は分かるんだけど、「岩盤保守」とは? 「堅固な保守思想層」なら分かるけど> @tanakatatsuo note.com/tanakatatsuo/n…
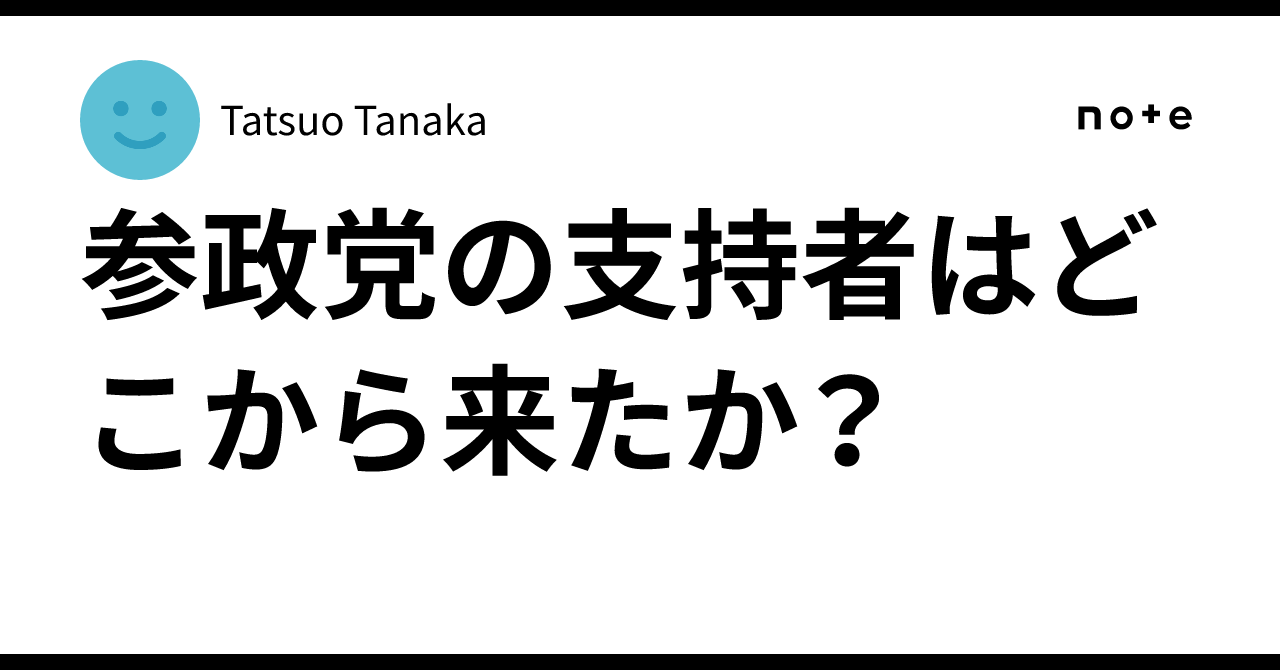
アンソロピック社による機械学習についてフェア・ユースを認めた判決: 原告は、自身の書籍の競合品が爆発的に作成されることによる市場への影響を指摘したが、裁判所は、創作的表現が類似ないものによる競争からの保護を著作権法は法目的としていないと述べている。
①クラウド・ロッカーに情報を保存した場合よりも、プライバシーが期待できないという話なのか、②前記①は期待できるけど、それを越えて法的に守秘義務のある専門家と同レベルは期待できないという話なのか、でかなり違ってくるんだけど、どっちだろう?
ChatGPTにあなたの秘密をペラペラ明かさない方が良い--サム・アルトマン氏も危惧 japan.cnet.com/article/352359…
文書化しても、向こうはいつでも前言撤回するはず。そのとき、こちらも同じ次元で撤回できるか? 文書化されてて拘束力があって云々と躊躇するのが目に見えてるんだから、ない方がこっちに有利なんだよね。 通常の外交交渉とか、ビジネス交渉とは違う、特別な文脈なんだと言うことを理解しないとね。
この分析、私もアグリーですね。 重要なのは、大統領が納得して、関税引き下げの大統領令にサインしてくれること。 それ以上に突っ込むのは両国とも問題を抱えてる。そもそも、文書化して拘束力を持たせようとする理由がわからない。 拘束力のあるWTO協定とかでさえ一顧だにしない相手なんだから。
この分析、私もアグリーですね。 重要なのは、大統領が納得して、関税引き下げの大統領令にサインしてくれること。 それ以上に突っ込むのは両国とも問題を抱えてる。そもそも、文書化して拘束力を持たせようとする理由がわからない。 拘束力のあるWTO協定とかでさえ一顧だにしない相手なんだから。
アメリカとの関西交渉の合意形成にたいてですが、米国の関税は通商拡大法第232を使っているので大統領令だけでできますが、日本との投資計画部分については、枠組み自体が2国間投資協定、特に投資仲裁制度を導入しないとできない話なので、大統領令で合意文書出せない(上院承認が必要)と思います。…
私見では、ある人物識別情報が個人の人格の象徴か否かは、本人の主観で決まる問題ではなくて、当該人物識別情報が、個人が人として尊重される基礎であるといえることが前提であり、尊重とは個人と社会との関わりの中で生じるものであるから、社会的にそう認識されるかどうかが鍵になると考えている。
欠陥というのは、人物識別情報ならそれでパブリシティ権の保護対象となるとする部分。 最判の論理は、人物識別情報であることを前提とした上で、個人の人格の象徴と言えるかを求めている。 声が保護されるとする結論は変わらないが、前者は、パブリシティ権の外延をあやふやにするリスキーな論理。
欠陥というのは、人物識別情報ならそれでパブリシティ権の保護対象となるとする部分。 最判の論理は、人物識別情報であることを前提とした上で、個人の人格の象徴と言えるかを求めている。 声が保護されるとする結論は変わらないが、前者は、パブリシティ権の外延をあやふやにするリスキーな論理。
今、声がパブリシティ権で保護されるとする見解の主要根拠は、ピンク・レディー事件最判の調査官解説の記述とそれを支持する学説。裁判例はない。 しかも、調査官解説の記述には、最判の論理と解離している、ある種の重大な欠陥がある。 なので、せめて、東京地裁の知財部の裁判例が欲しい。
今、声がパブリシティ権で保護されるとする見解の主要根拠は、ピンク・レディー事件最判の調査官解説の記述とそれを支持する学説。裁判例はない。 しかも、調査官解説の記述には、最判の論理と解離している、ある種の重大な欠陥がある。 なので、せめて、東京地裁の知財部の裁判例が欲しい。
この問題、詳しくはeprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/…の講演録(特に127〜130頁)にまとめてあります。また、30条の4・47条の5使い分け説と30条の4単独適用説(については問題点)に関しては103〜117頁に詳しく論じてます。
生成AI登場以来の、機械学習と著作権に関する議論、ボタンの掛け違えは、30条の4に議論が集中したことだと思う。 47条の5との使い分けをもっと議論してれば、権利保護面では、robots.txt対応とか海賊版学習の抑制とかが結構実現できてたし、利用面では、享受目的併存時も安心できる場面が増えたはず。
しかも、30条の4の但し書きに、過大な期待が寄せられたのも一因。30条の4だけ取り出して但し書きを読むと、活用できそうに思うけど、立法過程からの位置づけを踏まえると、本来使い勝手が悪い規定だし、47条の5の但し書きとの比較からは、海賊版対応は期待薄なこと明らかな規定なんだよね。
生成AI登場以来の、機械学習と著作権に関する議論、ボタンの掛け違えは、30条の4に議論が集中したことだと思う。 47条の5との使い分けをもっと議論してれば、権利保護面では、robots.txt対応とか海賊版学習の抑制とかが結構実現できてたし、利用面では、享受目的併存時も安心できる場面が増えたはず。
生成AI登場以来の、機械学習と著作権に関する議論、ボタンの掛け違えは、30条の4に議論が集中したことだと思う。 47条の5との使い分けをもっと議論してれば、権利保護面では、robots.txt対応とか海賊版学習の抑制とかが結構実現できてたし、利用面では、享受目的併存時も安心できる場面が増えたはず。
