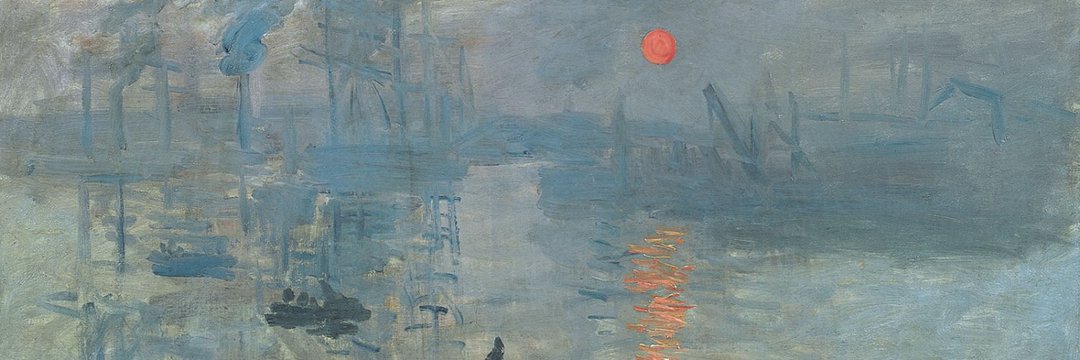
蓮見スイ
@HasumiSuis
衒学おじさん 本紹介など zinbun @web_zinbun amazonアソシエイト利用 何かあれば [email protected]
「ポジティブさ」という有害性 ポジティブ崇拝とネガティブ崇拝|蓮見スイ @HasumiSuis note.com/hasumisuis/n/n…
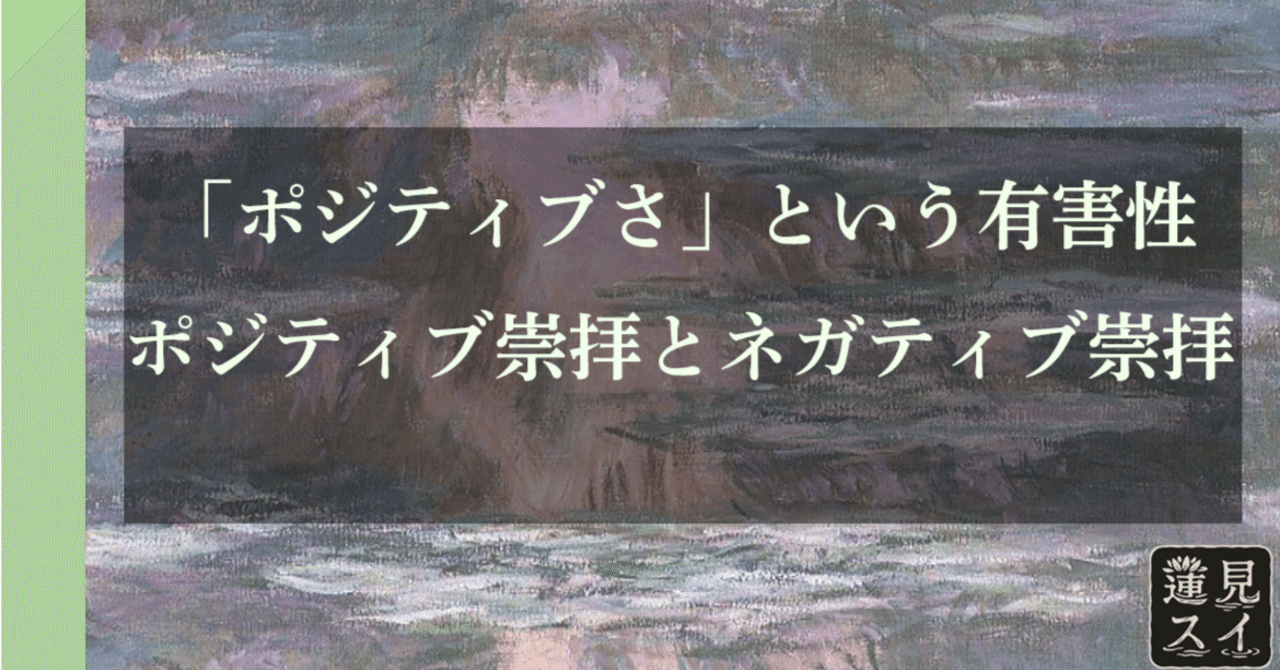
大塚英志の『物語消費論』ってビックリマンチョコレートという極めて身近な商品から、オタク文化に存在する「小さな物語」の集合によって「大きな物語」が作られていくという二次創作の仕組みについて分析していったのが本当に良く出来てるなあと感嘆する。
AIって、ハルシネーションを起こすから答えのある問題を解くのには実は向いていなくて、誰も答えを出せないような複雑な問いに対して、アイデアを出してくれるところに価値がある。 AIには正確性よりも思想的なものを書かせたほうがよっぽど上手く運用できる。
コスパを求めるのはほどほどにして、泥臭く努力するのが何だかんだ効率良いと気が付いた。 コスパってどこかで頭打ちして、コスパ追求する労力の方が大きくなって逆にコスパが落ちる。 コスパ追求が、実際に手を動かさない言い訳にもなりかねない。 コスパ追求は、現実逃避になってしまうこともある。
この世界って、個人の正解が社会の不正解みたいなものが多すぎる。 利己的になれば幸せになれるけれど、それは同時に周りを不幸せにするか、そもそもその方法を使える人間が限られていたりする。
現代は、今を生きる、未来を生きるのではなく、終わってしまった人生をどのようにけりをつけるかが1つのテーマになっている。 一億総クリエイター時代によって生み出された、クリエイター、「何者」になれなかった人がどうやって生きていくべきなのか。 「生」ではなく「喪」が大きなテーマ。
クリエイティブ職に就かなかった(あるいは就きたかったのに就けなかった)サブカル系の人々のその後の人生について興味がある
一億総クリエイター時代って、全ての人をクリエイターに駆り立てるのは良いのだけれど、クリエイターになれなかった人のケアがまるで抜けている。 もちろん以前よりクリエイター人口は増えたが、一億人すべてがクリエイターになれるわけがない。 なれなかった人間は負け犬意識を植え付けられるのに。
山崎まさよしの『セロリ』、 「育ってきた環境が違うから、好き嫌いはイナメナイ」 って分かり合えなさを伝えるけれど、 「がんばってみるよ やれるだけ」 「がんばってみてよ 少しだけ」 って、それでもお互いを理解しようとする努力を伝えてるところに良さがある。
現代人にとって就活はもはや、終活に近くて、老後の先取りなんだろうなと思ったりする。 社会の歯車として自分を殺しながら生きていくのが分かってるから、出来るだけ楽な仕事を。やりがいも、自己実現も果たされない。 学生というユートピアから追放された終末感と厭世観で包み込まれてると思う。